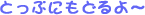わたしはナユちゃん!
第弐拾話「いい旅夢気分(前編)」
名雪「ねえ祐一。この道で合ってるのかなぁ?」
祐一「さあな。俺にもわからん。でも、道を走ってればどっかに出るだろ」
名雪「でもさあ、これってどう見ても獣道だよ? ナビにも道の表示出てないし」
俺達は道に迷っていた。
事の経緯はこうだ。
数ヶ月前に、突然秋子さんが、
秋子「名雪、祐一さん。アメリカへ行って、国際A級ライセンス、取ってきてもらえませんか?」
そう、謎ジャムをちらつかせながらのたまったのだ。
もちろん俺達に拒否権というものも、人権というものも存在しなかった。
断れば即・・・この先は言えない。
とにかく、俺と名雪はすぐさま秋子さんのチャーターしたコンコルドでアメリカへ飛び、
死に物狂いで国際A級ライセンスを取得してきた。
特に名雪の猛勉強振りには鬼気迫るものがあった。
どうやら無敵の破壊神の名雪でも、あのジャムの恐怖はDNAに刻み込まれているらしい。
期日までに取得出来なくても謎ジャムの恐怖。
あの日々は地獄でしかなかった。
何故突然国際A級ライセンスを取りに行かされるのか、
その事を秋子さんに訊いてみた所、
秋子「そろそろ、貴方達に私の『ホワイト・アウト』を受け継いでもらおうと思いまして」
『ホワイト・アウト』秋子さんの所有している車の事だった。
車種はホワイトのR32スカイラインGTR。
外見は普通のR32らしいが、中身のエンジンがまったくの別物らしい。
燃料はガソリンらしいが、最大馬力はドラッグレースカー並の1200馬力。
他にも様々な機能がついているらしいのだが、恐くて訊けなかった。
通常は普通のR32なのだが、ハンドルに付いている隠しボタン一つで化物カーに早変わりだそうだ。
そのあまりの化物振りに、全国の走り屋の間で、『ホワイト・アウト』と呼ばれているらしい。
理由は簡単。スタートと同時に一瞬で相手の前から消え去るように走り去るからである。
そしてその車を扱うにはそれなりの技量が必要。という事らしい。
で、無事国際A級ライセンスを取得してきた俺達に秋子さんは、
秋子「二人とも頑張りましたね。じゃあ、お祝いと慣らし運転も兼ねて、二人っきりで旅行にでも行ってきたらどうですか?」
本当の目的はこれだったんじゃないか?
と思いつつも、俺達は車で旅行に出かけたのだ。
んで、現在俺達はナビがあるのに道に迷って獣道を走っている。と、こういうわけだ。
祐一「しっかしこの車、ホントにじゃじゃ馬だよなぁ。向こうで足代わりにしてたフェラーリのがまだ可愛いぜ」
獣道の為、ガタガタ揺れるハンドルを必死に押さえつけながら愚痴る。
名雪「そうだよね。私もポルシェ運転してたから、少しは慣れてたつもりだったけど・・・この子は凄いね」
祐一「まったく、バーストモードを使ってないのにこの加速力にスピードかよ。恐れ入ったな」
バーストモードとはこの車の本気モードだ。
そんな車で獣道を走っているのだから、俺の実力もそこそこ捨てたものではないのだろう。
祐一「で、どうすんだ? この近くに舗装された道路って無いのか?」
運転中にナビを見るわけにもいけないので、代わりに名雪に問い掛ける。
名雪「う〜ん・・・無いよ〜。周り全部山だよ〜」
祐一「ゲ・・・どうすんだよ・・・って、なんか建物っぽいのが見えてきたぞ?」
名雪「えっ? うそ?」
ナビを凝視していた名雪が驚いて顔を上げる。
そこには、大きな赤い壁のような建造物が迫っていた。
祐一「かなり大きいな・・・おっ、なんか入り口みたいなのが見えるぞ?」
名雪「え? どこっ? どこっ??」
祐一「ほら、あそこの下の方。なんかトンネルみたいな入り口があるだろ?」
ハンドルから片手を離して指差す。
そこには、少し小さいながらもトンネルのような穴がぽっかり空いていた。
名雪「あ、ホントだ〜。・・・ねえ、あそこに入ってみない?」
祐一「う〜ん・・・そうだな。この際面白そうだから行ってみるか」
そう言うやいなや、俺をアクセルを深く倒し、スピードを上げた。
名雪「わっ! 祐一! トンネルの前に石があるよ〜!」
祐一「何!? ブレーキ!!」
咄嗟にアクセルを離し、ブレーキペダルを思いっきり踏みこむ。
スピードが出た状態で急にブレーキを踏みこむとスピンを起こすが、そこはなんとか抑え込む。
車は、寸での所で石の手前で止まる事が出来た。
祐一「ふ〜・・・危なかった」
名雪「祐一〜、気をつけてよね〜。私すっごくビックリしたんだから」
祐一「すまん。まさかトンネルの手前に石があるなんて思わなかった」
肝を冷やしたのか、名雪が抗議してくるが、どうせ名雪も俺も、その程度の事では死にはしないのだが・・・
名雪「ね、祐一。あのトンネル、車で入れるかな?」
祐一「ん〜・・・多分大丈夫だろ。とりあえず、そっちのミラーたたんでくれ」
そう名雪に促しつつ、自分でも運転席の左側にあるサイドミラーをたたむ。
名雪「祐一、おっけ〜だよ〜」
名雪のその声を合図に、アクセルを少しずつ踏みこみ、車をトンネルの中に侵入させる。
トンネルは狭かったが、車が通れないほどではなかった。まあ、長いようなのでテクニックはいるだろうが。
しばらく車をゆっくり走らせていると、トンネルを抜け、古い駅の構内のような場所に出た。
名雪「わ〜・・・なんか、古いけど綺麗な建物だね〜」
名雪がそう素直な感想を述べるが、そんな場所を車で走ってる事にはなんとも思わないのだろうか?
名雪「わっ! 祐一、段差があるよ〜」
祐一「ちっ! バルーンタイヤ!」
名雪が段差に気付いてを声を上げるが、冷静にバルーンタイヤのボタンを押す。
この車に付いている機能の一つだ。
見た目がかなりカッコ悪い為、あまり使いたくは無いが・・・
名雪「そんな贅沢言ってる暇無いよ〜」
どうやらまた声に出ていたらしい。
段差をバルーンタイヤで乗り切ると、所々に廃墟のような建物が目立つ広い草原が目の前に広がった。
名雪「わ〜・・・広くて気持ち良さそうだね。祐一♪」
祐一「そうだな。こんなとこで寝そべって昼寝したいよな〜」
名雪「でもさ、こういうとこ見るとさ、無性に破壊したくならない?」
祐一「するな!!」
スパーン!
と、軽いく乾いた音が車内に響いた。
名雪「うー・・・冗談だよ祐一〜。それに、ハリセンなんてどこに持ってたの?」
祐一「それは、秘密です♪」
名雪「うー・・・獣王に使える神官の真似なんて似合わないお〜」
スパン!
2度目のハリセンの炸裂音が車内に響いた。
祐一「ごちゃごちゃ言ってないで、ほら、なんか見えてきたぞ」
名雪「うにゅ?」
バルーンタイヤで岩場を越えると、なにやら街が見えてきた。
祐一「ラッキーだな。街がある。どっかに泊まれるホテルとか旅館とか無いかな?」
名雪「・・・なんか、錆びれた温泉街って感じがするよ〜」
祐一「っていうか、なんか中華街にも似てるような・・・まあ、どこかに車を止めて、行ってみるか」
車を止め、街に入ってみると、そこには人っ子一人、誰も居なかった。
名雪「誰も居ないねぇ」
祐一「むう・・・もしかして廃墟なのか?」
名雪「そうなのかも・・・困ったねぇ」
祐一「どうしたもんかなぁ・・・って、ん? なんか、食い物の匂いしないか?」
名雪「え? あ、ホントだ〜」
俺に言われ、名雪が鼻をスンスンと、可愛く動かす。
と、その匂いに気付いたようだ。
祐一「食い物があるってことは、人がいるはずだし、行ってみるか」
名雪「そうだね〜」
名雪と二人で、食い物の匂いの出所を探す。
少し歩くと場所は見つかった。が、
祐一「誰かいませんかーっ!?」
名雪「すみませーん! うにゅ・・・誰も居ないね」
祐一「食い物だけあって、人が居ないなんてなぁ・・・少し待ってみるか。そのうち戻ってくるかもしれないし」
名雪「そうだね。作ってそのままって、もったないしね」
なんか論点がズレてるが、その辺は名雪なので気にしない。
そのまましばらく店の人が帰ってくるのを待ってみるが・・・
名雪「帰ってこないね〜」
祐一「人の気配がまったく無いもんな。一体何が起こったんだか・・・とりあえず、他探してみるか」
名雪「う〜ん・・・そうだね。なんかちょっともったいないけど」
やはり論点がズレているが、気にしてはダメだ。
それから少し歩いてみると、油と書かれた旗が目にとまった。
祐一「油? 油って・・・あの油だよな?」
名雪「うん。そうだと思うけど・・・あ、あの橋の向こうの建物、煙突から煙が出てるよ!」
祐一「お、ちょっと行ってみるか、今度こそ人が居るかもしれないしな」
そう言って、少し急ぎ足で橋に向かうと、目の前に突然少年が現れた。
名雪「わっ!」
少年「なっ!? 何故また人間が・・・とにかく、ココから早く離れなさい!」
名雪が突然の事に驚いていると、少年は何か驚愕したような表情で、焦っているかのように言葉をまくし立てた。
祐一「離れろって・・・なあ君? この辺で宿泊できる施設しらないかな?」
少年「そんなことはどうでもいい! 早く立ち去りなさい!」
祐一「う〜ん・・・どうでも良くはないんだけどなぁ・・・って、おっ」
名雪「どうしたの? 祐一?」
少年が大声を張り上げて去れ! と言っているが、その時俺は、煙突に湯と書いてある事に気付いた。
祐一「なあ? ここって旅館じゃないの?」
少年「いいから日が沈む前に! 早く!」
名雪「・・・もう沈みそうだけど?」
飲食店で長く待ちすぎたのか、もう日が沈む寸前だった。
少年「・・・・・・」
少年がその場にガックリと膝を折る。
なにか酷く落胆させてしまったようだ。
なにか口が微妙に動いているので、何か呟いているようだ。
少年「千尋の時といい、また人間が来るとは・・・いや、人間が来る事自体は珍しくも無いか・・・」
そうこうしているうちに完全に日が沈む。
すると、旅館の提灯に火が灯り、街の赤い提灯にも日が灯り始めた。
祐一「お、これから営業なのか。よし、行ってみよう」
名雪「あ、祐一待ってよ〜」
少年の横を素通りして歩き始めると、後ろから今気付いたのか、名雪が急いで駆け寄ってきた。
少年は今も何かをブツブツ呟いていた。
とりあえず無視して旅館の暖簾をくぐる。
『いらっしゃいませー!』
と、従業員が営業スマイルで向かえてくれたが、俺達の姿を見て、そのスマイルが一瞬で固まる。
祐一「あの〜。二名程、泊めてもらいたいんですが・・・」
『に、人間ーっ!?!?』
名雪「わわっ」
従業員一同、声をそろえて大絶叫。
名雪が驚いて躓きそうになる。
『(ど、どうする?)(どうするたって、千以外に人間が来たのは久しぶりだぞ)(湯婆婆様に知らせるか?)』
祐一「あの〜?」
倒れそうになった名雪を支えつつ、円陣を組んで何やらヒソヒソ話をしている従業員達に声を掛ける。
が、まったく聞こえていないようだ。
?「人間だってぇぇぇぇっ!?」
従業員A「ゆ、湯婆婆(ゆば〜ば)様・・・」
従業員達がヒソヒソ話しをしていると、建物の上の方から従業員達とは違う、威厳の感じられる大声が響いた。
途端に上から頭の大きい老婆が飛び降りてきた。着地の瞬間、スピードを緩和したように見えたので、何かあるのかもしれない。
その湯婆婆と呼ばれた老婆は、俺達をジロジロと、まるで目利きするような目で睨んだ。
湯婆婆「ホントに人間だねぇ。さてどうするか・・・」
祐一「お婆さん、この旅館の女将か? すまないんだが、俺達二人泊めてもらえないか?」
俺達を睨んで何か思案していた湯婆婆に泊めてもらえないかと訊いてみる。
湯婆婆「人間を泊めるぅ? はっ! 馬鹿言ってんじゃないよ。ここは八百万の神様達が疲れを癒しに来る御湯屋なんだ。
人間なんざ泊められるわけないだろう。人間はね、ココじゃ豚になるしかないのさ」
ビシ!
湯婆婆がその一言を言った瞬間、玄関口の空気が瞬時に凍りついた。
ヤバイ! 俺も少しはムカっときたが、俺の隣りに居る人物は、俺の比じゃない!
名雪「お婆さん・・・ちょっと・・・来てもらえるかな?」
ヤバイヤバイ! 名雪既にブチ切れ状態じゃんか。
ああ、神様。どうか、どうか俺に平穏をください・・・
俺が神に祈りながら突っ立っていると、名雪が有無を言わさぬ絶対零度の笑顔で、
湯婆婆の頭をむんずと掴み、外へ引っ張り出していった。
祐一「あ! 名雪! ちょ、ちょっとまったぁっ!」
俺が気付いた時には、その場に名雪はおらず、凍りついたままの従業員達がその場にたたずんでいただけだった。
急いで外に駆け出すと、そこには・・・
名雪「お婆さん・・・誰にそんな口聞いてるのかな? 私に豚になれ? 塵になりたいのかな?」
絶対零度の笑顔で微笑みつつ、天上天下一撃必殺砲を湯婆婆に突き付ける名雪。
湯婆婆の方はというと、何故か余裕の笑みだった。
あの名雪を前にして、余裕でいられるとは・・・大したばーさんだ。
だが、時にはそれが命取りになる事を知ってほしいもんだ。
湯婆婆「おやおや、人間風情が偉そうだねぇ。今すぐ豚に変えて欲しいみたいだねぇ」
湯婆婆がニヤリと不気味に笑い、腕を動かそうとすると・・・
ズギャァァァァァァァァァァァァァァァァッ!!!!
名雪が躊躇いも無く天上天下一撃必殺砲のトリガーを引き、膨大なエネルギーが湯婆婆の左頬付近をギリギリ接触しないで、
周囲の空間を焼き払いながら直進した。
名雪「動いちゃダメだよ? ・・・お婆さん」
そう名雪が言った瞬間、辺りが閃光に包まれた。
カッ! ドゴォォォォォォォォォォォッ!!!
閃光が収まると、湯婆婆の後方にあった島が一つ消し飛んでいた。
当たってはいないものの、左に飛び出ていた髪の毛を根こそぎ焼き払われた湯婆婆は、
今度こそ、顔面蒼白になって震えていた。
湯婆婆「こ、この私が、人間相手に恐怖を感じるなんて・・・」
底知れぬ威圧感と恐怖。それが今の名雪にはあった。
まだ居たのか、橋の真中で膝をついて天を仰いでいた少年も、膝をついたまま青くなって震えていた。
湯婆婆「くっ・・・この!」
祐一「よせっ!!」
ズギャァァァァァァァァァッ!! カキィィィィン!
悪態ついて腕を動かそうとした湯婆婆をまた膨大なエネルギーが襲う。
今度は湯婆婆に照準を合わせていたので、咄嗟に俺はATフィールドを全開にし湯婆婆の前に飛びこみ、斜めに傾けて攻撃を上に逸らす。
名雪「祐一・・・何するのかな? そのお婆さんは私と祐一を豚にして、私達の仲を裂こうとするんだよ? 塵にしておかなきゃ・・・」
祐一「えーい! 目を覚ませ名雪ぃぃっ!!」
スッパーン!!
今迄で一際大きいハリセンの音が辺りに響いた。
名雪「痛い・・・んん・・・あ、あれ? 祐一? 何してるの?」
名雪が片手で頭を摩りながら、困惑顔で首を傾げる。
どうやら正気に戻ったようだ。
祐一「ふ〜・・・とりあえず一安心か。で、ばーさん! あんた死にたいのか!? 何が出来るのか知らんが、
さっきの名雪に刃向かうのは死と同義語だぞ! 頼むから、俺達を一晩泊めてくれ」
湯婆婆「くっ・・・分ったよ。好きにしな・・・但し、ちゃんと金は払ってもらうよ」
祐一「すまないな。大丈夫、金はちゃんとある」
湯婆婆「言っとくけど、人間の貨幣はお断りだよ。ここでの金は、金(きん)の事を言うんだ」
祐一「そうか。なら、これで足りるだろう」
湯婆婆に向かって、5kgの金のインゴットを投げる。
それを受け取った瞬間、湯婆婆の目の色が変わった。ように見えた。
そして次の瞬間、湯婆婆は旅館の中に消えていた。
湯婆婆「さあお前達! 人間とはいえ、これだけの金を出した大切なお客様だ! 丁重におもてなししな!!」
『は、はいっ!』
どうやら従業員達に激を飛ばしているようだ。
奮発したかいがあったな。
なんとか、まっとうな扱いをしてもらえるらしい。
少年「貴方達は一体何者なのですか? 湯婆婆様に人間が太刀打ち出来るとは・・・」
ようやく立ち直ったのか、少年が疑惑の篭った眼差しで俺と名雪を交互に見ていた。
ま、気持ちはわからんでもないが。
祐一「あのばーさんがどんな事が出来るのか知らんが・・・この宇宙に名雪に勝てる存在(もの)は居ないぞ」
名雪「うー。祐一〜、人を化物みたいに言わないでよ〜」
何時の間にか、俺の隣りで名雪が頬を膨らませていた。
う〜ん・・・実際、化物の方が名雪よりマシだと思うんだが・・・これは言わないでおく。
言ったら機嫌を直らせるのが大変になる。
祐一「ま、いいじゃないか。泊まれる事にはなったんだ。温泉旅行と洒落こもうぜ」
名雪「うー・・・なんか誤魔化された気がするけど・・・うんっ」
不満顔ではあったが、温泉の魔力に負けたのか、最後にはとびきりの笑顔で頷いた。
こう言う所は凄く可愛いんだけどなぁ・・・ま、いいか。
少年「待ってください! 湯婆婆は魔女です。悪い事は言いません。今のうちに立ち去るべきです」
祐一「へぇ。あのばーさん魔女だったのか。まあ、神様が居るくらいだ、魔女くらい居るだろうな」
少年「なっ? 貴方達は湯婆婆の恐ろしさが分らないんですか!?」
祐一「恐ろしいって・・・なあ名雪?」
名雪「全然恐くないね」
祐一「それに、これくらいなら俺にも出来る」
少年に手を翳し、魔法を唱える。
瞬時に少年の姿は豚に変わってしまった。
何やら驚いて叫んでいるが、豚な状態なのでプギープギー五月蝿いだけだった。
祐一「慌てるな、直ぐ戻す」
手を翳してもう一度同じ魔法を唱える。
すると少年は元の姿に戻った。
祐一「これで分ってもらえたか? ・・・え〜と、君、名前は?」
少年「あ、はい。ハク(珀)と申します」
祐一「じゃあハク。これであのばーさんが恐ろしくない理由、分ってもらえたか?」
ハク「はい。どうぞごゆっくりしていってください」
そう言うとハクは旅館の中に消えて行き、その場には俺達だけが残った。
祐一「じゃ、俺達も行くか」
名雪「うんっ」
名雪が頷いて腕を絡めてきた。慣れてはいるが、それでも顔が赤みをおびるのは仕方ない事だろう。
二人腕を組んで再度旅館の暖簾をくぐると、少し引き攣った営業スマイルを浮かべている従業員が向かえてくれた。
まあ、これも仕方ない事か。俺はそう思って諦める事にした。
その頃、湯婆婆は自分の部屋に父役と兄役を呼びつけて何か指示をしていた。
湯婆婆「いいかい。表向きは丁重にもてなすんだ。だが、料理は別料金と偽り、金をふんだくった後、料理で豚にしてしまいな」
父役「はっ、かしこまりました」
兄役「ですが、人間風情がこの湯屋に泊まるなどと、他のお客様に知れたら・・・」
湯婆婆「そうだね・・・あの二人は最上級の部屋に泊めな。それだけの金はいただいてるしね。そうすれば、他のお客様に見られる事も無いだろう」
兄役「かしこまりました。そう致します」
湯婆婆「くっくっくっくっくっ・・・はぁーっはっはっはっはっ!」
湯婆婆が勝ち誇った笑い声を突然上げる。
だが、この時ハク以外は気付いていない事が一つだけあった。
夜を過ぎているというのに、祐一と名雪の身体は消えそうにはなっていなかったということを。
ついでに、父役と兄役が不在であった為、下位の従業員達がてんてこまいだったことも。
つづく
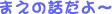
後書き
久々に長いナユちゃんです。
ホントはこのまま書ききっちゃうつもりだったのだけど、どう考えても
このまま書ききると50〜60KBいっちゃいそうなので別けました。
あと、書き方ちっと変えてみましたが、いかがなもんでしょ?
読みやすくはなったと思うんですが・・・
名雪「そんなことより・・・まず先に言わなきゃいけない事があるでしょ?」
ギク・・・な、名雪しゃん? なんの事ですかな?
名雪「すっとぼけても無駄だよ? これ、見てない人には思いっきりネタばれじゃん!」
えー・・・そう言われてもなぁ・・・書きたかったから書いたんだし。
見てる間からネタ考えてたし。
ついでだからこの後に、読みきりでGS美神のメンバをここに来させるつもりさね。
名雪「宮崎作品パクるなんて・・・筆者、ディズニー並に落ちたね」
失敬な! 私はパクってない! なんて言い張る程愚かじゃないぞ!
それに私は宮崎監督に敬意を表し、気に入ったからこそ、パロっているのだ!
っていうか舞台をそのまま借りたのだ!
あの今ではアニメ界の汚点でしかないディズニーなんかと一緒にするなぁっ!
名雪「はいはい。わかったよ」
むう、なんか納得イカンが、まあよかろう。
ではまた次回お会いしましょ〜。
名雪「今回ギャグが少なめでごめんね〜」
それを言うなぁっ!!